映画「ヘルムート・ニュートンと12人の女たち」は、ファッション写真家ヘルムート・ニュートンを「すごい写真家だった」と持ち上げて終わる作品ではありません。
ヘルムート・ニュートンと仕事をした女性たちが、撮影現場で何を求められたのか、どこが面白かったのか、どこが嫌だったのかを、揃わない言葉で語り続けます。
そこにスーザン・ソンタグの批判映像まで入るので、観る側も落ち着きません。
この記事では、まずヘルムート・ニュートンのプロフィールを時系列で整理します。
ベルリンで生まれ、迫害から逃れて国を出た経緯、ジューン・ニュートンとの出会い、ヴォーグやプレイボーイで仕事を重ねた流れ、2004年の事故死までを分かりやすくまとめます。
そのうえで、映画がどこを強調し、どこを削っているのかを「映画と実話の比較」として紹介します。
映画を観て引っかかった人が、ヘルムート・ニュートンの全体像を自分の言葉で整理できるように書いていきます。
映画「ヘルムート・ニュートンと12人の女たち」ヘルムート・ニュートンのプロフィール!

ヘルムート・ニュートンは1920年にドイツのベルリンで生まれています。
ベルリンで育ち、若いころから写真へ向かいます。
ただ、ベルリンで写真を学べる時代は長く続きません。
ナチスによるユダヤ人迫害が強まり、ヘルムート・ニュートンは1938年にドイツを離れます。
映画でも終盤にさらっと触れますが、この出来事は「転職」や「引っ越し」ではなく「生き残るための移動」です。
この背景を知ると、ヘルムート・ニュートンの写真に出てくる冷たい緊張の理由が少しだけ見えます。
笑顔の写真が少ない、という単純な話ではありません。
光が当たっていても空気が固い。あの固さが、後から効いてきます。
オーストラリアでジューン・ニュートンと出会い、仕事と生活が一体になる
ドイツを出たヘルムート・ニュートンはヨーロッパを離れ、オーストラリアに渡り、ジューン・ブラウンと出会います。
結婚後、ジューン・ブラウンはジューン・ニュートンとして映画に登場します。
映画の中でジューン・ニュートンは、撮影現場の空気を「妻の感想」ではなく「現場の記録」として語ります。
長身の女性が好きだったこと、ヌードばかり撮るので周囲から遊び人扱いされたこと、嫉妬するのかと何度も聞かれたこと。
どれも、言い方が生々しいです。
さらに重要なのは、ジューン・ニュートン自身も撮る側になっていく点です。
夫婦が同じ現場にいて、同じ人間を見て、違う距離から記録する。
この関係があるから、ヘルムート・ニュートンの人物像は「女性を撮る男」で固定されません。
ヴォーグやプレイボーイで名を上げ、ヌードと挑発がセットで語られるようになった
ヘルムート・ニュートンはヴォーグやプレイボーイなどで女性を撮り続け、ファッション写真の世界で強い存在感を持つようになります。
ヘルムート・ニュートンの写真は、服を見せるだけの写真とは違います。
視線が強い。立ち方が硬い。ハイヒールが武器みたいに見える。
部屋の奥行きが怖い。そういう要素が重なって、見た人の身体が先に反応します。
一方で、ヘルムート・ニュートンの写真は長年批判も受けます。
ポルノまがい、女性嫌悪、支配の匂いがある。
映画がそこを避けないのは良い点です。避けると嘘になります。
実際に揉めたからです。
自分はここで「挑発」という言葉が便利すぎると思いました。
挑発と言うと綺麗に片づくけれど、写真を見た側が感じるのはもっと直接的です。
嫌だ、気持ち悪い、怖い、でも目を離せない。
その連続です。
2004年の事故死と、ベルリンの財団が残した作品の置き場所
ヘルムート・ニュートンは2004年に交通事故で亡くなります。
場所はハリウッドで、映画はその最期まで触れます。
ジューン・ニュートンが「死に顔を覗き込む写真を撮った」と語る場面は、個人的に一番冷えました。
愛しているから撮ったのか、撮る人だから撮ったのか、その境目が揺れるからです。
ベルリンにはヘルムート・ニュートン財団があり、作品は保存され展示され続けます。
展示されるということは、肯定と批判の両方がこれからも続くということです。
ヘルムート・ニュートンの写真は、時間が経てば丸くなる種類ではありません。
むしろ、時代が変わるほど質問が増えます。
映画「ヘルムート・ニュートンと12人の女たち」とは?
映画の作りを押さえると、どこが刺さってどこで疲れるのかが分かります。
12人の女性の証言
映画の中心はヘルムート・ニュートン本人の武勇伝ではありません。
ヘルムート・ニュートンと仕事をした女性の証言が中心です。
シャーロット・ランプリング、イザベラ・ロッセリーニ、グレイス・ジョーンズ、クラウディア・シファー、ナジャ・アウアマン、ハンナ・シグラ、マリアンヌ・フェイスフル、シガニー・ウィーバーなどが登場し、現場で起きたことをそれぞれの言葉で語ります。
証言が揃わないのが、この映画の一番きついところで、一番正直なところです。
気持ちよかったと言う人がいて、嫌だったと言う人がいて、面白かったと言う人がいて、もう二度とやりたくないと言いたげな顔も出ます。
現場はそうなるよな、と納得してしまいます。
撮影の具体例
映画は具体例を次々に出します。
シガニー・ウィーバーの丸刈り頭と黒いタイツの撮影は、モノクロで撮る話として出てきます。
写真の目的が「役の記録」ではなく「姿の圧」になっているのが分かります。
グレイス・ジョーンズの話はもっと直接的です。
自然光を使い、ヌードの一瞬を狙い、ナイフを持たせる。
ナイフの意味は見る側に任せると言う。こういう構図の狙いは分かります。
でも分かった瞬間に落ち着くわけではありません。
むしろ、落ち着けなくなる。
さらに、宝石とチキンの話が出ます。
ブルガリの高価な宝石をつけた手に、脚付きチキンを持たせる。
高級品の世界に油と匂いを持ち込むようなやり方です。
関係者が卒倒しただろうと言うけれど、ヘルムート・ニュートンは面白がっている。
ここで、ヘルムート・ニュートンが「上品にまとめる人」ではないことが確定します。
「使う側」「嫌う側」
映画が賢いのは、撮られた側だけで終わらせない点です。
アナ・ウィンターが登場し、雑誌の編集長としてヘルムート・ニュートンの写真を必要とした理由を話します。
読者の反応が欲しい、記憶に残る写真が欲しい、そのためにヘルムート・ニュートンに頼む。言い方が仕事の人です。
そしてスーザン・ソンタグの討論映像が入ります。
スーザン・ソンタグはヘルムート・ニュートンの写真を女性蔑視だと批判し、遠慮しません。
司会者が困るくらい強い言葉が出ます。
この映像が入ることで、映画の中に逃げ道がなくなります。
ヘルムート・ニュートンの写真を「かっこいい」で済ませることも、「芸術だから」で押し切ることもできなくなります。
自分はここで一回止まりました。止まって、また再生しました。嫌でも考えさせられます。
ジューン・ニュートンの存在
映画はずっと刺激の強い話を続けますが、最後まで冷たくはしません。
理由はジューン・ニュートンです。
ジューン・ニュートンが語るのは、現場の裏話だけではありません。
ヘルムート・ニュートンがどういう人間として生活していたか、どういう誤解を受けていたか、夫婦としてどう過ごしていたか。
周囲の証言も重なり、ニュートン夫妻が敬意のある関係だったと語られます。
ここがあるから、ヘルムート・ニュートンは「女性を支配する側」とだけは言い切れなくなります。
言い切れなくなる瞬間が生まれる。映画はそこを狙っています。
映画「ヘルムート・ニュートンと12人の女たち」の実話の比較も紹介



ここから映画と現実の違いを具体的に並べます。
仕事の範囲の見せ方が違う
実際のヘルムート・ニュートンは、ファッション、広告、肖像、男性被写体、都市風景など幅広く撮影しています。
映画はその中から「女性写真」と「ヌード」「挑発的構図」に集中します。
つまり、現実の活動範囲は横に広いのに、映画は縦に深く掘っています。
間違いではありませんが、偏りはあります。
映画だけ観ると、ヘルムート・ニュートンは常に過激な写真を撮っていた人に見えます。
時系列よりテーマ優先で並べ替えている
実際の経歴は年代順に積み上がっていますが、映画はテーマ順に並べ替えています。
ベルリン時代、移住、雑誌仕事、展覧会という順番ではなく、証言とエピソードの強さで配置します。
そのため、観る側はヘルムート・ニュートンのキャリアの伸び方より、「どんな写真を撮ったか」「どう揉めたか」を先に覚えます。
ここは映画的な編集です。
人物像のバランス調整が入っている
現実のヘルムート・ニュートンには、仕事仲間、編集者、男性モデル、クライアントとの関係もあります。
映画はそこをほぼ削り、ジューン・ニュートンと女性被写体に集中します。
その代わり、ジューン・ニュートンの証言を厚く入れて、家庭と人柄の側面を補強します。
結果として映画のヘルムート・ニュートンは、「挑発的な写真家」+「理解あるパートナーと暮らした人物」という形でバランスを取られています。
ここは編集による人物調整です。
まとめ
映画「ヘルムート・ニュートンと12人の女たち」は、観終わったあとに「好きだった」で閉じられません。
「嫌だった」でも閉じにくいです。
自分は観ながら何度か顔がしかめっ面になりました。
グレイス・ジョーンズの鎖の話で一度止まり、スーザン・ソンタグの討論で口が固まり、宝石とチキンの話で笑っていいのか迷いました。
でも、その迷いが残ること自体が、この映画の狙いだと思います。
ヘルムート・ニュートンの写真は、見る側に反応を出させます。
目をそらす、怒る、笑う、考える。
そのどれでもいいから反応しろ、と迫ってきます。映画も同じ動きをします。
だからこの記事の最後はこれで締めます。
ヘルムート・ニュートンを天才と呼ぶか、女性嫌悪と呼ぶか、その結論を急がなくていいです。
代わりに、どこで嫌だったのか、どこで面白かったのか、どこで笑いそうになったのかを一つずつ言葉にすると、ヘルムート・ニュートンの写真が「ただ強い写真」ではなく「自分の感情を引っぱり出した写真」に変わります。
映画「ヘルムート・ニュートンと12人の女たち」は、ヘルムート・ニュートンのプロフィールを知ってから観ると、ベルリンから逃げた過去、ジューン・ニュートンと現場を積み重ねた生活、ハリウッドで終わった最期までが、写真の硬い光とつながって見えます。
気分が良くなる映画ではありません。
でも、観終わったあとに誰かと話したくなる映画でした。
実話映画をジャンル別にまとめた一覧ページはこちらです。
ほかの実話映画も探したい場合は、こちらの記事からチェックできます。
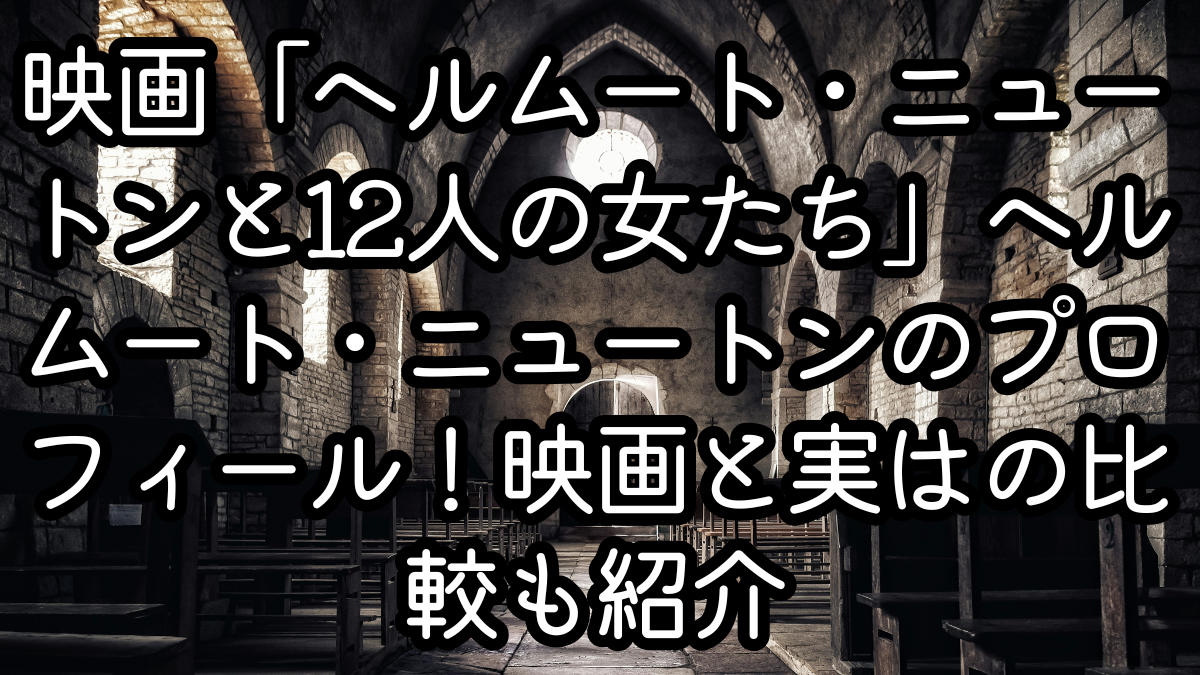
コメント